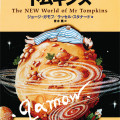『親のための新しい音楽の教科書』
若尾裕:著
サボテン書房:刊
ISBN:978-4-908040-00-9 C0073
臨床音楽学の専門家である著者が、子どもと音楽の関係から、日本人のいびつな音楽観を問う。
小学、中学生時代の音楽の授業というと、あのイヤな体験が思い出される。縦笛の発表である。一人ずつ立って、みんなの前で吹いてみせるやつだ。あがり症の友人の発表なぞ、見ているほうもつらい。練習で上手に演奏できていたのに、緊張のあまり音が震えて息継ぎが途切れ、曲の最後まで辿りつけるのか、それとも気絶するんじゃないか。こんなに恥ずかしい体験をさせて「音を楽しむ」なんて授業と言えるのかと子供ながらに考えていた。
本書が問うているのは、このような音楽体験、音楽教育のあり方である。縦笛の発表のように、楽器を演奏する、歌うといった音楽の体験を「恥かしいもの」「みっともないもの」にしてしまったのはなぜか。それは明治以降の学校での音楽教育にあったのではないか、という指摘だ。つまり政府が教育システムを作り上げる時、近代化を焦るあまり音楽から疎外される人々が多く発生してしまったという指摘だ。
かつての日本では、音楽と私たちの生活は結びついたものであり、地元で歌い継がれる民謡があった。そこに明治政府が導入した音楽の授業が入ってくる。耳慣れない西洋式の「唱歌」を強制される。この時、日本に「音痴」が生まれたというのだ。
つまり、聴き慣れないドレミファソラシド、という西洋音階で構成される音楽に、すべての日本人がすぐに馴染めるはずがない。 しかし明治の音楽教育は、唱歌を歌えない人を音痴と呼び、軽視した。文部省も、音階や定拍リズムを身につけない子どもには悪い成績をつけるべし、という指導を行った。こうして歌を歌うこと、演奏することが、恐ろしく恥ずかしい体験となって人々に蓄積されてきた。つまり音楽教育を 通じて西洋化にすぐに順応できた人間が、それに対応しきれない日本人を文化的に辱めていたのではないか、と。
本書では、このように現在の音楽教育を「はずかしい音楽」「むずかしい音楽」「へたくそな音楽」そして「こども用の音楽」「楽しい音楽」という章を立てて、歴史的、社会的な分析を加えながら音楽を解説してゆく。クラシック音楽=むずかしい音楽、 という図式はなぜ定着したのか。小学校低学年では「かっこうワルツ」を楽しめればよいが、高学年になったら「交響詩モルダウ」のような長い音楽を理解しましょう、という「やさし い音楽から難しい音楽へ」という段階的カリキュラムには、なんらかの正当性があるのか? なぜ教科書にビートルズの曲が掲 載されても、ローリングストーンズは掲載されないのか? なぜ学校教育に音楽の授業が必要なのか?
本書は子供の音楽教育について、具体的に親がどうすべきなのかというという答えは用意してくれない。答は筆者が与えてくれる補助線を参考にしながら、私たちが考えなければいけない。音楽とはなんなのか? なぜ音楽を子どもに楽しませたいのか? そもそも親が子どもに音楽を学ばせることに、はたして意味があるのだろうか? 文章は分かりやすく、中学生なら理解できる内容だ。 だから、学校で習う音楽がツマラナイな、と感じている子にも本書をお勧めする。
最後に、本書に紹介されているこんなエピソードが印象深かったので紹介しておく。大作曲家モーツァルトの父の話だ。彼は息子を自分と同じ、地方都市の裕福な音楽家として育てようと音楽の早期教育を受けさせた。しかし父の目論見は失敗した。息子は父の言うことは聞かず、父を捨て、放蕩の結果、若くして死んだ。モーツァルトは子供の頃の早期教育でヨーロッパ各地を巡り、当時の最先端音楽に数多く触れたことで、才能は花開き、もはや田舎音楽家の父の手中などにはいられなくなったのだ。教育はそんな側面だってある。音楽ファンとしてはモーツァルトの父に大いに感謝しなければならないのだが。
★2015年2月20日発行 ココカラ本誌12号の掲載記事を再録しました。
文:大杉信雄
1965年、三重県生まれ。
良いデザイン、優れたインターフェイス、使う楽しさを与えてくれる製品を集めた提案型の販売店「アシストオン」店主。
http://www.assiston.co.jp
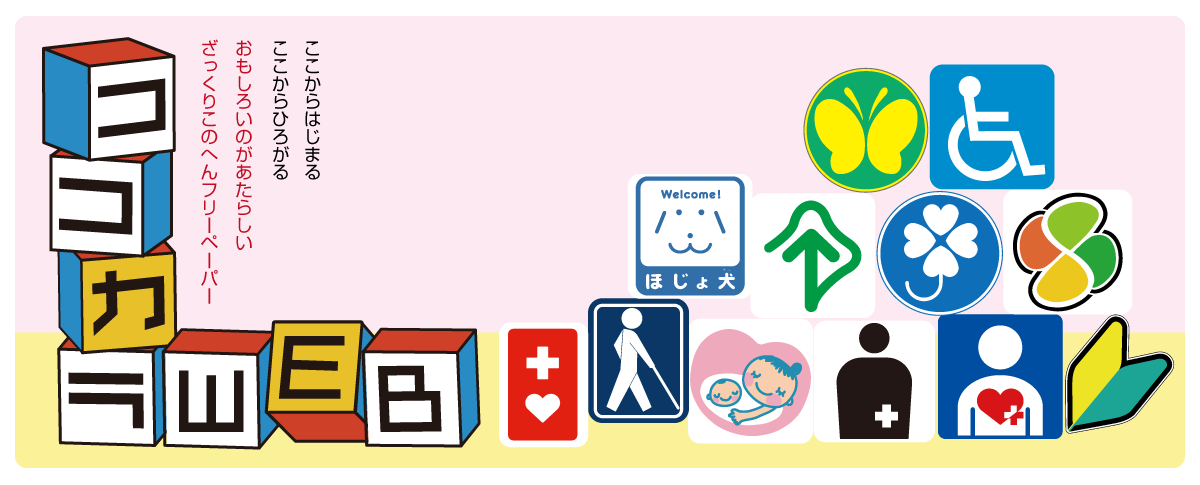


 Follow
Follow