はつねで一番旨いのは、じつは「ラーメン」である。タンメンも旨いが、何を置いても醤油味の、あっさりしたラーメンが旨い。
最近の、豚骨醤油とか煮干し系とか、そういうガッツリした味ではない。荻窪ラーメンのようなものとも少し違う。品のいい、雑味の少ないスープと、生醤油の風味。なましょうゆではないぞ、きじょうゆだぞ。
ともすれば、ラーメン評論家やラーメン好きには「味が無い」「スープ薄い」と言われるようなスープに、中華鍋で茹でられた麺が入り、かつては竹輪の薄切りが多かったが最近は鯛入りかまぼこ、おそらく鯛と言ってもイトヨリダイとか、そういった決して高くも特別でもないものが乗り、あっさりした味の煮豚、いんげんかえんどう、海苔、そしてネギのみじん切りである。メンマすらない。

俺は、このラーメンを食べるときには、孤独のグルメの原作者、久住昌之さんよろしく「ダンドリ」がある。
まず、手を合わせて「いただきます」。
そして、海苔をスープの海に沈める。
映画「たんぽぽ」じゃないけれど。具も全体にスープに軽くしずめてから、れんげでスープをひとすくい。そこで「うん、今日も旨い」と思ってから麺をすすり始めるのである。海苔は、スープの中で少し戻すと、生海苔とは行かないが、海苔ならではの食感と香りが戻ってくる。煮豚は冷蔵庫に入っていたので、スープで少し温度が上がると柔らかくなる。
はじめての人には、一口めは薄いと感じられるかも知れないスープだが、食べ進んでいくと、だんだん口の中にうまみや塩気、香りが拡がり、スープを最後に全部飲みきると、ちょうどいい味なのである。
日本料理の花形である「椀」がそうで、吸い口のだしといいながら、それは食べ終わり、だしをすべて飲みきったところでちょうどいい塩加減にするのが最上と言われる。東京の人間は、俺を含めて「鰹の香り」を好むが、京都の料理は、鰹の香りでも昆布の香りでもない「だしの香り」がする。
はつねの醤油ラーメンは、まさにそういうものなのだ。
どんぶりを手に持って、スープを最後の一口まで\イヲみきったら、箸を置き、手を合わせて「ごちそうさま」と声に出す。
完璧である。
一杯のラーメンという、完全なる宇宙である。
はつねは、じつはもう十年くらい前か、代が変わった。
おやじさんとおかみさんの間には、娘さんがいた。その娘さんの結婚相手がいまのご主人である。わかりにくいので、「はつねさん」と呼ぼう。
はつねさんは、もとは日本料理をしていたとおかみさんから聞いている。たしか、一度自分でも店を持ったはずだ。ちらしをもらった記憶がある。ちょっと離れていたので行けないうちに、ある日、はつねに親父さん同様、五厘刈りにした若い男性がいたのでおやと思い聞いてみたら、いまのはつねさんだった。おやじさんの横で、じっと仕事を見ながら、最初はどんぶりを洗い、カウンターを拭き、水を出していたが、すぐにおやじさんと一緒に仕事をするようになり、あれよあれよという間に、おやじさんと交代で店に立つことになった。
ある日行くと、おかみさんとはつねさんの二人だけである。おやじさんは、と尋ねると、こっそり「そろそろ店を任せようと思って」と言う。
ほどなくして、おかみさんの代わりに、娘さんが店に立つことが増え、いつの間にか、おかみさんも、おやじさんも、娘とその連れ合いさんに店を引き継ぐ形になった。
はつねさんは、おやじさんにくらべて若いから、土日が休みだった店を、日曜だけ休むことに切り替えた。いまは、月に何日かは連休を取っているようだけれど、平日の昼間しかやっていなかった頃に比べると、遠くから客も来るようになった。
俺があちこちで言いふらしたせいで、タンメンが大人気になってしまった。
でも、はつねさんは、若いから、営業時間もすこし伸びた。3時くらいには閉まっていたのだが、いまは4時過ぎまでやっている。そのあと、暗くなっても、はつねさんは店を掃除して、仕込みをしている。
おやじさんと同じ仕事をしている。例えば、春以外の固い時期のキャベツは、芯に近いところは薄く切る。固くてたべられないところは、汚れを落とし、シッポだけ切って、スープの中に入れる。「始末のいい仕事」である。
麺を茹でる片手の北京鍋はいつも綺麗で、何杯か茹でるとお湯を替えるので、かん水臭いラーメンにならない。
チャーシューは煮豚で、もも辺りの肉だから、脂は少ないけれど、少し固い。なので、チャーシューを切ったときに、少し隠し包丁を入れる。
俺は、もう五年ほど前に口の中の癌で入院していて、そのときにどうしてもはつねのラーメンが食べたくて、外出許可を取って西新宿の病院から西荻窪まで行ったことがある。その時、上あごには歯が二本しか無かった。病気だからしょうが無いが、まだ義顎ができていなくて、ほとんどモノが噛めない状態だ。
それを察したはつねさんは、いつもよりちいさく煮豚を切って、隠し包丁をより細かく丹念に入れて出してくれた。
その後、月に一度ほど訪れてもいつもこう声を掛けてくれた。
「また、小さく切りますか?」
いまはもう、すっかり人並みのものを食べられるようになった俺は、それでも、あの時のはつねさんの思いやりを、一生忘れない。
喰いものやは、代が変わると常連が離れる。
はつねも、おやじさんが引退したとき、一瞬、ちょっと暇になったことがある。と言っても、行列の長さが短くなった程度だが。
俺がいつものようにラーメンを食べていたら、別の常連客と思しき男性が「おやじさんのころとは味が変わったねえ」と言った。
その時、おかみおさんは、ぴしゃりと切り返した。
「いいえ、なにひとつ変わっちゃいません。うちの人は、全部教えきりましたから。ずっとはつねの味ですよ」
その毅然とした口調と、厳しい目を見て、その常連はすごすごと帰って行った。
実際には、はつねさんの代になって、ほんの少し、味は変わったと思う。スープはシャープになった。タンメンの塩の香りが鋭くなった。麺のゆであがりがしゃきっとした。醤油の味が背筋が伸びたようにしっかりした。つまりは、旨くなった。
でも、それはまぎれもなく、はつねの味だ。
おかみさんは、はつねさんと娘さんに店を譲って、ほどなく亡くなったと聞いている。
でも、いま、二人が店に立っていると、それはおやじさんとおかみさんが若い頃には、こうだったんだろうな、というたたずまいである。
登亭は店を継ぐ人がいなくてたたんでしまったけれど、はつねは、こうやって続いている。登亭がいい店の終わり方をしたというならば、はつねは、いい店の継ぎ方をした。
俺は、自分が死ぬ前の、最後のラーメンははつねにしようと決めている。
俺が死ぬまで、続いてください。
文:坂井淳一
「職業は酔っぱらい」を自認するフードジャーナリスト。光文社BRIOの食べ歩き記事をはじめ、多くの雑誌でのレストランガイドを担当。「東京感動料理店」(共著)なども。「今日は何を呑もう」からメニューを考える「酒ごはん研究所」主任研究員。
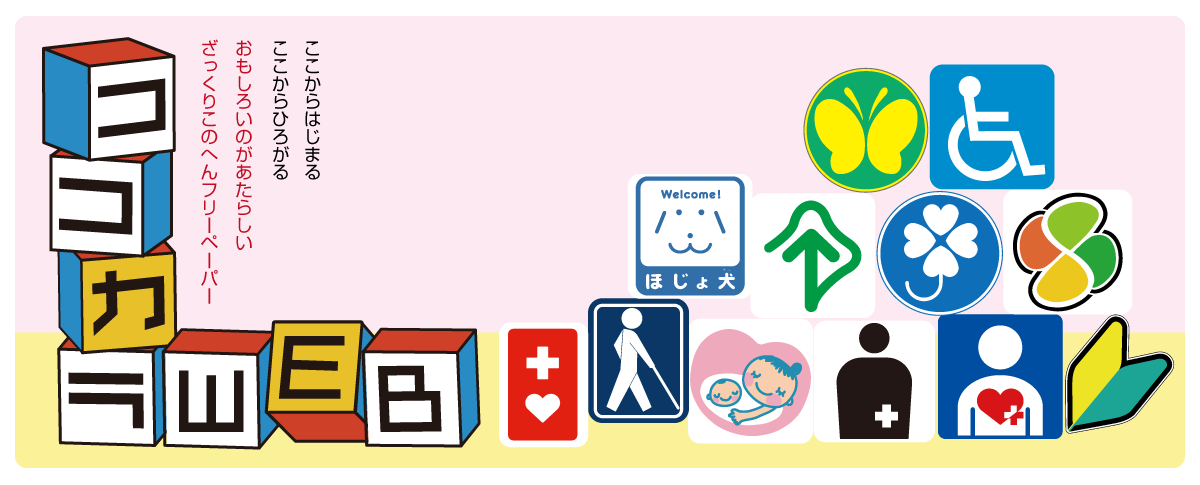
 Follow
Follow


