美しい釣り、というものがある。
ノーマン・マクリーンが書いた小説『マクリーンの川』は、堅実で、きまじめな兄の視点から奔放で自由であり人気者の弟との葛藤を描いた素晴らしい小説だ。『A River Runs Through It』という作品名でロバート・レッドフォードの手で映画化され、弟役を若いブラッド・ピットが演じて話題になった。レッドフォードは、若かった頃の自分の「美しさ」をブラッド・ピットに重ね、その若く、純粋で、傍若無人な無邪気さを巧みに演じさせた。
この作品の中心にあるのは「川」であり、フライフィッシングである。
フライフィッシングは、およそ「釣り」という趣味の中でも、格段に気位が高い。ライブベイト、つまり活きている餌を使わないことを素晴らしいものとしているのはまさにフライフィッシャーのプライドで、この作品の中でも、愚鈍で女にだらしない男が一緒に釣りに行くと言っていたが、彼の「餌」を見て鼻で嗤うというシーンがある。
この映画で、何よりも素晴らしいのは、フライフィッシングにシンパシーがある人間にとっては少し陳腐でもあるのだが、自由で奔放な弟がフライフィッシングの奥義に目覚め、川の中に立ち続け、素晴らしいキャスティングをするシーンだ。
逆光でブラッド・ピットの姿と、ロッドと、ラインが光り、美しい弧を描いてしなやかにラインが伸びる。
この風景の中に自分を起きたいと、全てのフライフィッシャーが夢想するほどの美しさである。
釣りは戦術と戦略だ、という人がいる。
よりたくさんの魚をいかにして釣るかが重要だという人もいる。
より細い糸で、より大きな魚を「獲る」のかが醍醐味だという釣り師もいる。
俺の心の師のひとり、開高健は、大きくても、小さくても、ともかく一尾を手にすること。ゼロと一の間は果てしなく広く、一から先はおまけだ、というようなことを言っている。
それぞれに、正解だ。釣りは、いろいろな形があっていい。
けれど、その中に、フィールドに溶け込むこと、風景のかけらになることを追い求めた釣りがある。
それが、美しい釣りだ。
兵庫県の明石を中心に昔から行われている釣りに、「海老撒き」という釣法がある。
琵琶湖や沼にいるシラサエビ、ブツエビという二種類の「活きた海老」を使う釣りだ。
大きく「播淡」と呼ぶこともあるこの地域では、元々こうした海老が豊富で、ゴカイやイソメなどと並んで、釣り餌として手頃だったようだ。
この活きた海老を、活きたまま海まで持っていき、ぱらぱらと撒く。磯釣りや波止(はと:防波堤のことを、このあたりではこう呼ぶ)の釣りでは、今はもうすっかり撒き餌は冷凍のアミエビとか集魚材が一般的になってしまったが、この活きた海老を撒いて魚を釣る、というのには「集魚力」とは違う意味合いがある。
湖産、つまりは淡水の海老で、居酒屋で「川海老の唐揚げ」と言って出てくるあの海老なのだが、海に撒かれても、しばらく海老は生き続ける。アミエビは死んでいるから、撒かれた瞬間、それは実は海を汚す要因になるし、集魚材も同様である。程度はあるが、一時、メジナなど磯の上物釣りがブームになった時に磯の臭いや、そればかりを口にしている魚の食味についてもいろいろ言われたことがある。今でも鯛釣りでは、コマセ場に集まる鯛より、活き海老や「ひとつテンヤ」などで釣った鯛の方が味がいいと言われる。
このシラサ海老やブツエビは、先ほども言ったように、しばらく活きている。テトラポットや岩の間に入り込んで活きているので、それを狙って様々な魚が居着く。結果、その釣り場には、常に外から魚がやってきて、よく釣れるし、魚が撒き餌くさくもならない。防波堤が汚れることもない。いま撒いている海老は、次の人のため、というとても合理的な釣りなのである。「飼いつけの釣りだ」という人もいるほどである。
釣れる魚種も様々で、夏の間は「朝ハネ」と言って、スズキの若魚を狙う釣りがある。東では、フッコというくらいのサイズで、昔は50センチくらいまでの魚はスズキとは呼ばなかった。そのくらいのスズキを、あのへんでは「ハネ」と呼ぶ。これはファイターで、引き味も良く、かかった鈎を外そうと、海面でエラ洗いと呼ばれるジャンプをする。
周年、特に秋から春までの海が寒い時期に人気があるのが、チヌ、つまり黒鯛である。黒鯛は悪食で、海が汚い場所の魚は「猫またぎ」と言われるほどだが、潮通しのいい海で釣れた黒鯛はとても美味しい。普段食べているのがシラサエビなら特に、である。
そして、なによりも、この釣りで俺が好きなのは、メバルである。小さい魚だけれど、食味もよく、煮付けが一般的だが少し大きくなると刺身も格別にうまい。
魚屋に行くと赤いのをメバルと言って売っているが、あれは住んでいる場所も違う。あれも美味しいが、やはり釣って楽しいのはクロメバルである。名の通り黒や黒金色の魚で、大きな目が愛らしい。
愛らしい魚を食べてしまうのだから罪だが。
身はふっくらとして、繊維がきめ細やか、けれどふわふわとおぼつかないモノではなく、小さな魚なのに、身に野生を感じる力強さがある。
東京湾奥、羽田あたりでも釣れるが、あれは油臭くていけない。東京湾なら、横浜、本牧や金沢八景より南の地域で獲れた魚が美味しい。
春先の一時、逗子や葉山あたりからは、イワシメバル、ドジョウメバルといった、活きたイワシやドジョウを餌にして釣るメバル釣りの船が出てそれも楽しい。今は渡れなくなってしまった東京湾の第三海堡あたりでは、黒鯛釣りのゲストに、一尺を超えるメバルが釣れたりもして、それは黒鯛よりも価値があると言われたものだ。最近では、ルアー釣りのターゲットとしても人気がある。
けれど、やはり明石や、向かいの淡路島北側の波止で、海老撒きで釣るメバルほど楽しいものはない。
伝統的な海老撒き釣りは、なにより道具立てが素晴らしいのである。
まず、餌のシラサエビを活かしておく道具。
いまでは、ブクブクと呼ばれるエアポンプ付の小さなクーラーを持っていくのが一般的だが、好き者たちは、そんな「文明の利器」は使わない。
「海老箱」という道具を使う。
これは、大小あるが、大きいものは縦長の20リッターくらいのクーラーと同じくらいの大きさ、小さいものはうんと小ぶりの、木製の箱である。肩から掛けられるように、ベルトが通してある。
上蓋を開けると道具入れになっているものもあるが、その下に氷を入れる空間がある。そして、横を見ると、三段から五段ほどの引き出しが設えられている。この引き出しを引くと底には網が張ってある。
1段で一杯から二杯。シラサエビは枡で量り売りで、一杯500円ほどで売られているのだが、それを入れてキツキツにならない大きさになっていることが多い。ちなみに、東京で活きた海老を買うと、1尾30円から50円というとてつもない値段が付けられている。少し大きいこともあるが、これを撒くのは、いくら地球に優しかろうとも、懐には優しくない。
その日の釣りの狙いや時間に応じて、餌屋でシラサエビを買い、上蓋から氷を入れる。
すると、氷は自然に溶けて、ぽたぽたと冷たい水が下に落ちる。これを浴びた海老は、冷たいので仮死状態になり、おとなしくなる。けれど、死んではいない。
釣り場に行ったら、まずその海老をパラパラと撒く。そして魚を寄せる。氷が溶けきるまでは、ずっと海老に冷たい水が落ちるので、鮮度を保てる、という仕組の優れた道具である。もちろん、たいていのクーラーと同じように、椅子として座ることも出来るし、モノによっては釣った魚を氷を入れたところにしまえるものもある。ただし、たくさんは入らない。食べられるだけ持ち帰れ、と言われているようでもある。
長い浮きを使う。そして、小さい鈎、細い糸、柔らかい竿、軽い仕掛けである。メバルは目がいいので、糸が太いとなかなか食いついてくれない。
竿も、今ではお手軽に、カーボンの磯竿を使う人が多いのだが、好き者たちはそんなことはしない。
ヘラブナを釣るための竹製の和竿をベースにした、長くて、ぶらぶらして、柔らかい、十五尺から十八尺の竿を使う。それに、小さい両軸型のリールを付ける。遠くに仕掛けを投げるためではなく、水深や釣り場に合わせて糸を出すためのものなので性能はあまり気にしない。むしろ、軽くて一日竿を振っても疲れないものを選ぶ。竿はカーボン製ではないのでそれなりに重いし、ぶらぶらしているのもある。それ以上に、大きなリールはみっともない、というプライドがあるのかも知れない。
そして、釣り方がおもしろい。
ぱらぱらと海老を撒きながら、尾羽を切った海老を鈎に付け、仕掛けを振り込む。
魚が居れば、海老を突っつく前アタリが出る。そこで合わせてしまってはいけない。たいていは釣れない。我慢をすると、浮きがすっと水中に入り込む。しかし、ここで合わせてもいけない。なぜなら、メバルが鈎を飲み込んでしまうからだ。大きな魚なら、それは食べればいいことだが、小さな魚だとハリを外す時のダメージで死んでしまうことも多いので、良くない。
では、いつ合わせるのか。
浮きがぐっ、ぐっと本アタリを示した後、さらに待っているとぎゅーんと海中に沈む。
そこから、一呼吸置いて。これが肝心だ。
ゆっくり、大きく合わせるのだ。
竿の柔らかさと鈎の小ささ、合わせるスピードなど、全てが作用して、メバルの口の端に綺麗に鈎がかかる。つまり、あわせこそ、海老撒きでのメバル釣りの極意なのである。
メバルは、小さいけれど、引きが強い魚だ。けれど、しょせんは小魚、カーボンの強い竿を使えば、あっという間に寄ってしまう。
けれどぶらぶらの竹竿だと、15センチほどの小さなメバルでも、ほどよく引いて、竿を綺麗に曲げてくれる。竹竿独特の粘りがあるので、その引き気味を楽しんでいると、魚が自然と手元に寄ってくる、という寸法である。
明石の俺の釣りの師匠は、この竿でチヌも狙う。尺を越えると、チヌなら、糸が切れるか、竿が折れるで、と笑いながら釣りをする。
彼は、その竿で尺を越える黒鯛も取りこむのだ。最後は玉網を使うが。
それが、腕である。
釣りは、心はアマチュア、腕はプロ、というのが理想である。面倒臭い釣りの方が楽しい。難しく釣る方が楽しい。一つ一つの道具を吟味して釣る方が楽しい。旧いスポーツカーが、今のファミリーカーより遅くても、運転が楽しいのと一緒だ。
魚が釣れることが楽しいのではなく、釣りをすることが楽しいのだ。
彼は、美しい釣りをする。
波止の上やテトラの上に海老箱を置き、そこに座る。その姿が、まず凛としている。時折引き出しから海老を取り出して撒き、脇に竿を抱えて小さな鈎にシラサエビを付け、仕掛けを振り込む。
この一連の動作を繰り返し行う。まるで茶道の所作を見ているようである。一連の動きが流れるようで、無駄な力がどこにも入っていない。
ぶらぶらの和竿は、軽い仕掛けを思い通りの場所に振り込むのが難しい。今時のカーボンの竿なら簡単なことが、とても高いハードルになるのである。
少し竿を長くとった仕掛けを、大きなのの字を描いて、竹の弱い弾力をうまく使いながら、鞭のように竿をしならせて振り込む。
朝陽を背に浮き上がるその姿。
ああこれは、ブラッド・ピットのあのシーンと重なるではないか。
彼は、釣りが大好きで、竿も自分で作るほど病んでいる。浮きも、海老箱も、自分で作ったり、手を入れている。ひとつひとつに彼の想いが込められ、それを携えて釣り場に立ち、一枚の絵になることが、おそらく彼の「釣り」なのだ。
俺はと言えば、なかなかそこまで行くことは当然できない。
ポケットにはスキットルが入っている。シングルモルト、バーボン、ラム。酒は様々だ。
そしてスペインのシェリー蔵、オズボルネに行った時、スーベニールショップで買った、ステンレス製の折りたたみのカップがある。
寒ければ、酒を呑む。
暑ければ、海老箱の中に忍ばせていた、よく冷えたビールを飲む。
あまつさえ、夏であれば、クルマに七輪を積んで、前の日に波止に乗り込み、そこで肉を焼きながら夜明けを待つというクズ野郎である。
駄目な釣り、嫌いではない。
釣りは、人生だし、俺の人生は寄り道だらけだからな。
文:坂井淳一
「職業は酔っぱらい」を自認するフードジャーナリスト。光文社BRIOの食べ歩き記事をはじめ、多くの雑誌でのレストランガイドを担当。「東京感動料理店」(共著)なども。「今日は何を呑もう」からメニューを考える「酒ごはん研究所」主任研究員。
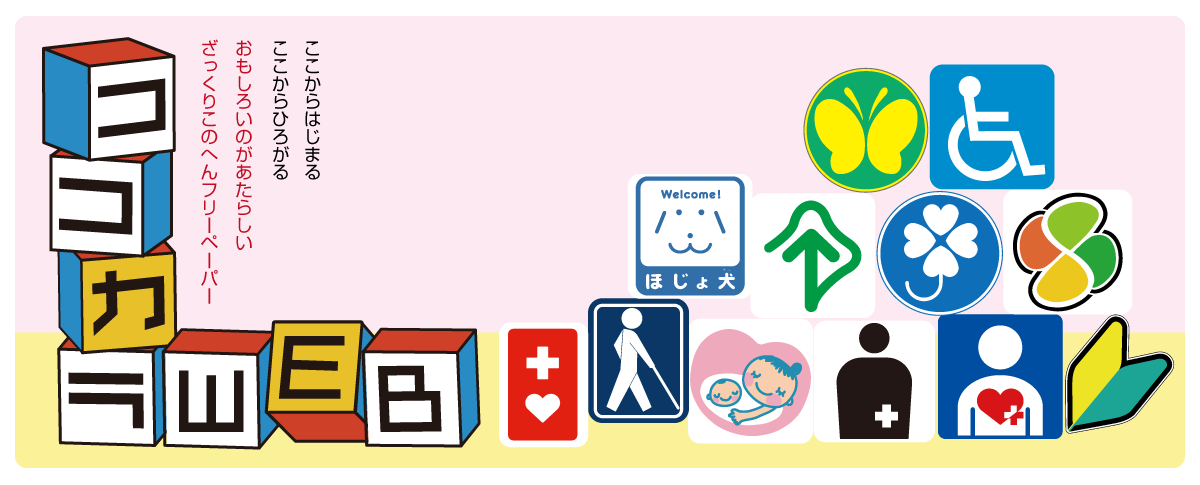



 Follow
Follow


