ミシュランの星付きの店が、どこも「おまかせのコース一本に絞っている」という話を、最近、聞いた。
日本料理は、そもそもおまかせが基本だし、エル・ブジが小さいポーションの多皿料理を流行らせてからというもの、ヨーロッパでもそういったスタイルの料理の出し方をする店が多くなったのは理解が出来なくもない。
理由は、いくつでも挙げられる。コース一本のみというのは、料理人の考え方がうまく反映される。食材のロスも少ない。予約を取っているから人数も分かっているし、あらかじめ下ごしらえが確実にできるから料理を遅滞なく出せる。星がたくさん付いている、いわゆる「グランメゾン」は、それなりに席数を持っているので、効率が良いというのが最大の理由なのだ。
食べ手の方からしても、一生に一度訪れるかどうか分からない店で、何を食べたら良いのかも分からないのだから、決まっていた方が楽だよな、そりゃあ。
でも、それは「おまかせ」じゃなく「お仕着せ」じゃないかという気がする。いわば既製服。
おまかせは、ビスポークであるべきだ。
というわけで、ちょっと「おまかせ」の楽しさを考えてみたい。
仕事をしていて「お前にまかせるわ」と言われることは多々あって、それは二つの意味を持っている。ひとつは、お前を信用しているから、良いものを上げてくれよ、というヤツ。もうひとつは「まあ、たいしたことが無い仕事だからどうでもいいよ、取りあえずスケジュールだけ守ってね、埋まってりゃあいいよ、というもの。いわゆる賑やかしだ。
俺は埋まってりゃいいよ、という仕事はしない。
なんてことはない。
金のためなら魂なんて売るさ。そうでもしないと酒が呑めないからな。
でも、売文業をしている時に気をつけているのは、つねに「埋めること」や「コスパ」じゃなく、どこか、おもしろみを盛り込むことだ。高い安いじゃなく、読んでいる人間に、いろんな罠を仕掛けて、そのどれかにはまってくれること。ギャラが安くても、プロだからさ、そこは妥協したくない。
おまかせ、というのはそういうものでなくちゃいけない。
自由にやらせてくれるのだから、その分、遊ぼう、という算段で仕事に臨まないと、次の注文が来なくなるのだ。
取りあえず埋めるものは、誰にでも「替え」がきくから、その分タメされると思った方がいいよ、フリーランスで生きて行きたいと思っている人。
それは、レストランでも、割烹でも、居酒屋でも同じことなのだ。
その店でなければならない、という皿がきちんとあることは、その店の価値をぐんと高められる。
居酒屋では「名物を四つ作れ」とよく言われる。三つでも良いけれど。取りあえず、その三つが食べたいという人は来るし、困った時にもそれがあるからふらっと立ち寄れる。間違いが無い。そして常連になると、それではつまらないからそれ以外のものを食べることになる。けれど、誰かを連れてきた時には、その名物を薦めれば、外れない。
レストランになると、それは「グランドメニュー」ということになる。
この店は夏なら冷製のカペリーニを食べろとか、この店は冬なら野ウサギのロワイヤルだ、とかいうアレである。星付きのレストランはそういうグランドメニューを持っているところが多いし、エル・ブジはそれを否定するところからスタートした。
ついこの間、最近遊んで貰っている女性に連れて行かれたワインバーのヘンタイ亭主はその逆で、決まったものを作りたくない、ワインと、それに合わせた料理を臨機応変に出していきたいと言っていたが、それはもちろん正解だ。
きわめて常連の比率が高く、しかも彼の考え方を理解した客が、それを求めてくるのだから、既にそのヘンタイ亭主のヘンタイ度合いが「名物」なのである。

つまりは、そういう店は、客を選ぶと言うことである。ただ「おいし〜い」と言って食べている人間には、その店の面白さは理解できない。
いや、グランドメニューを持つオーセンティックな、あるいはクラシカルなレストランにしても、それは同じ事だ。
メニューの中にずらりと書かれた料理名を見ても、なかなかどれを食べたら良いのか分からない、という人は多いのだが、それはきみの経験値が足りないだけだ。あるいは、想像力が。
グランメゾンは、本来その店ならではの「グランドメニュー」や「スペシャリテ」を持っている。繰り返すが、初めてならばそれをオーダーすれば良い。外れはない。それはたいていメインディッシュなので、そこに向かう筋道を考える。
ここからが、食べ手の熟練度を試されるフェイズだ。
どんな料理を頼むか、そしてどんな酒を選ぶか、ということに、メニューや分厚いワインリストを眺めながら、もちろん財布の厚さを考えてびくびくしながら、思いを馳せる瞬間が、じつはレストランの醍醐味なのである。
常に、酒を選ぶのも、料理を選ぶのも自分。
だから、選んだワインが傷んでいた、という事態ではない限り、料理も、酒もまずければそれは自分の人生が誤っていたということに他ならないのである。
もちろん、初めての店だったり、そういうことを知らないでも、楽しむことは出来る。分からなければ、サービスマンやソムリエに訊ねればいいだけのことだ。
彼らはサービスのプロだから、そういった客にいかに楽しんでもらえるか、そしてその客を見て、見込みがありそうなら、そこでそっとパスを出してくる。
「こういうことを知っていれば、もっと食べることは楽しくなりますよ」というプロの、正確で、素早いスルーパスである。勘の良い人間はそれを受け止めて、ゴールするだけでいい。ディフェンダーは、懐の中にいる「財布」というゴールキーパーだけだ。
ただね、そうやって、毎回料理も酒も事細かく選んでいくのは、時折疲れる。
そして、何度も同じ店に通っていると、飽きる。
料理も熟知しているし、ワインリストも知っている。なので、驚きを感じられなくなってくるのだ。
そんな時ですよ、おまかせ、という言葉が生きてくるのは。
きちんとしたサービスをするレストランならば、店の人間は、俺の好みや、今までに何を食べたか、呑んだかをおおよそ掴んでいる。日本料理屋なら、カウンターの向こうの板前が把握しているし、まじまじとは見ずとも、こちらの顔を見て、空気でその気分を察してくれる。
居酒屋はもちろん。自分の売りたいものを押しつけるのではなく、客の呑みたいものを推し量るのが、仕事だからな。
「今日は何がある? おまかせにするよ」
この言葉は、そういう店で、そういいう時にはじめて出てくる言葉だと言うわけだ。

六本木に「さだ吉 鎹」という、小体(こてい)な居酒屋がある。目抜き通りから一本裏道の地下にある店は、看板らしいものもろくに出ていないし、階段を下りていったところにある入口も怪しい店だ。
かつては、紹介のみで客を入れていた。亭主の三浦俊幸さんは一度店を離れ、長野で農業を始めたのだが、店が忙しくて手が足りないと呼び戻された。いまは、日曜日には長野に戻って畑を、営業日は店でサービスをやっている。いまは、紹介がなくともふらりと立ち寄れるようになったが、店の「姿勢」以前と変わらない。
ここはかつてうどんが名物で、三浦さんは「もともと讃岐のうどん」と言っているが、讃岐とも関西とも九州とも違う、独特な腰のうどんを昆布だけの精進のだしで食べさせていた。鰹と昆布のだしに慣れている人には、インパクトには欠けるので少し物足りないと思っていたかも知れないが、その昆布だしの丁寧な取り方、きめ細やかで複雑な旨味、昆布のかそけき香りに、俺はめろめろになっていた。そういう店だから、料理も面白くて、例えば夏になると、枝豆を炭で焼いて出したり、まあ次から次へとストライクを投げ込んでくるのだ。酒も、珍しいから、いま話題だから、という選び方ではなく、ありふれた銘柄からも、知られてない蔵からも引っ張って、うまく料理と合わせてくる。かといって「マリアージュがスゴイでしょう」という押しつけがましい主張もしてこない。すべてが控えめで、けれどきちんど考えると、なぜこの酒なのか、なぜこの食材でこの料理、そしてこの味なのかが理解できる、きわめて頭の良い店なのだ。
そんな店に、俺はクリスマスイブに、独りで行ったよ。
世の中はみんな幸せな気分に満ちあふれていて、もちろんフランス料理やイタリア料理のレストランは星付きからサイゼリヤまで人で一杯だったはずだ。きっと食材も上等だけれど、お値段はもっと上等なクリスマス特別メニューと言うお仕着せを楽しんでいるに違いない。まあそれで幸せになれる人はそれでいい。判で押したようにどの店でもフォアグラとトリュフは出てくるし、シャンパーニュもポンポン空く。何を食べるかよりも誰と食べるかが大切、なんていけしゃあしゃあと言っている人たちはそれでイイよ。
おれ、ひがんでるな。独りだから。
まあ、その日は、みんな恋人と予定があったり、家族と過ごしたり、クリスマスというのはそういう日だから、ぼっちで飯を食うという人間には肩身が狭い。心が寂しい。
ギルモアの「Wish you’re here」なんかを昼間聴いてしまったものだから、いてもたってもいられず、街に繰り出したのだ。青い空ですら心が痛いのに、明るい街の灯はどれだけ心に刺さるか。
三浦さんに連絡を取ったら「残念ながら……空いてます」という言葉が返ってきた。
その日、店には、常連と思しき女性がカウンターに一人、さっくりごはんを食べて、お店の二人にプレゼントを渡して帰って行った。あとは、テーブル席に座ったグループで、俺はぽっつりと独りでカウンターに座ったわけだ。
ええと。最初は、カバだったはずだ。カヴァともいうけれど、カバな。
「なんか、一杯、まずは」と伝えた。寂しくて死にそうではないけれど、考えるのはイヤだったので、考えてもらった。
まあ、クリスマスだからね。一人だけど、さだ吉さん、あえてこれを出してきたよ。これはイヤミなのか、思いやりなのか。
なぜ「三浦さん」ではなく「さだ吉さん」と書いたかというと、この店は、料理を作る女性と、三浦さんの掛け合いでやっているからだ。二人は、客前では打合せもしない。阿吽の呼吸で料理と酒が出てくる。
この店では、最初に、必ず三種類、小さな器に盛られた野菜の料理が出てくる。ゴボウの煮いたのだったり、ざっかけない、まあお通しのようなものなのだが、それが旨い。
その日の一皿、少し固めに煮かれたゴボウをかみしめると、醤油やだし、唐辛子のほんのりした辛みの向こうから、ゴボウ汁がやってくる。ゴボウならではの土くれめいた、野趣溢れる味である。そして、カバを一口呑むと、ゴボウの土の香りがふうわりと口の中に拡がるのだよ、きみ。
独りでいることは、もうその瞬間にどうでも良くなってきて、ああこの店は本当に俺の弱みを突いてくるなあと思った。
だから、小さいサイズのメニューは置いているし、それを見ながらの注文でもいいのだけれど、ここはゴボウとカバの直球を投げてきたさだ吉さんにこう言ったのだ。
「クリスマスだけれども、おれは独りだからさ。おなかはさほど空いていない。おまかせでね」
これは、俺のさだ吉に対する挑戦状でもあり、同時に信頼でもある。

例えば、ハゼが天ぷらで出てくる。
これは、秋にFacebookに書いた「多摩川の六郷土手に行ったけれど、台風の翌日で全部下流に流されていて坊主だった」という書き込みを見ているからかも知れない。たまたまその日、ハゼを仕入れていたということはあるだろうけれど、頭の中にそういう者があったからの「ハゼの天ぷら」である。
そしてそれに合わせての清酒が出てくる。珍しい酒でも、とびきりの酒でもないのだが、ほっこり落ち着ける、旨い酒である。
そんな「押し引き」を、カウンター越しにするのである。
この料理は旨いねえ、と言うだけではなく、ハゼはほっこりとしていて、でもキスとは違う独特の味わいがあるよねえ。落ちハゼの季節は仔で小さいからすみを作ったり、秋口に釣ったハゼを焼き枯らしにして、それを正月の雑煮のだしに使ったり……なんていう話が弾む。
そこから、季節の食材の話になり、三浦さんの長野の畑の話になり、若手の農業の担い手の話になったり、話題は拡がっていく。そんなとりとめのない会話に付き合ってくれるのもバーマンであった三浦さんの面白いところだ。
そしてかぶら蒸しや軽くしめた鯖、ちょっとだけまぐろなんかが出た後に東一の大吟醸とともに、プロシュートを出してくれた。この酒は、ごっつりとした味わいが好みの俺にとっては優しく、別嬪な酒である。別嬪ではあるが、側に別嬪さんはいないので、手を触れることが出来ない。そこで、プロシュートである。これを手で摘みながらの酒である。もちろん、料理屋だから、箸で食べるのが礼儀。けれども、カウンターに客は俺一人だし、なんかもうこころがぐだぐだに解けてしまっているので、手で摘まずにはいられない、そんなたたずまいである。別嬪が隣にいれば、彼女の頬に触れるだけでいいのだが、いないので、生ハムと酒、なのである。なんと言ってもクリスマスイブだ。

そして「昨日、お客様が予約をされたので、取りました。お肉はあいにく売り切れなんですが……」と出されたのは、すっぽんである。
卵と、内臓を煮いたものを片口様の小さな器に盛り込み、合わせて明鏡止水大吟醸m’14。決して高い酒ではないけれど、やはりこれも別嬪だなあ。アタリが柔らかくて、華やかさもあるけれど、鼻筋が通った美人だ。俺は鼻筋が通った美人が好きだからな。
料理も、酒も、すっかり堪能をした後で、ぼうっと思い出すのは今日の酒と、料理のことだ。
カバで始まって、すっぽんの卵と明鏡止水で打ち止め。
ふうむ。
今日のおまかせのテーマはなんだったのか、分かりやすいな。
ギルモアを聴いてすさんだ心をスパークリングで洗い流して、最後は鏡のような平らかな心で帰れよ、ということである。人生はまだ終わっていない、いのちを喰らって、新しい生を生きることが出来るぞということである。こういう気持ちを受け取ることが出来るから、おまかせというのは楽しい。
寂しい心に効くのは、デヴィッド・ギルモアでも、ロイ・オービンソンでもなく、おまかせの料理と酒である。
文:坂井淳一
「職業は酔っぱらい」を自認するフードジャーナリスト。光文社BRIOの食べ歩き記事をはじめ、多くの雑誌でのレストランガイドを担当。「東京感動料理店」(共著)なども。「今日は何を呑もう」からメニューを考える「酒ごはん研究所」主任研究員。
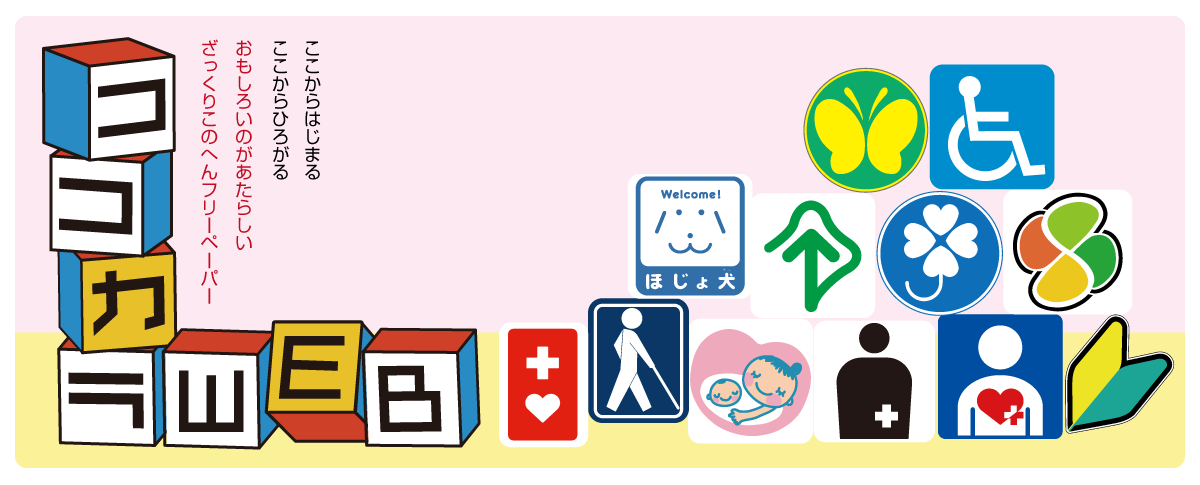
 Follow
Follow


