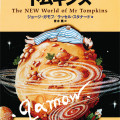「どんどん橋、落ちた」
綾辻行人
講談社文庫
歌舞伎の「仮名手本忠臣蔵」を見て、「史実と違う!」と劇場に怒鳴り込んだ人がいたという。歌舞伎は、元々、本当にあったことを演じてはいけない、という決まりがあって(当時の幕府から、そういう命令が出た)、史実と違うのなんて当たり前なのだけれど、まあ、人の見方は色々ということだろう。ただ、当時のマスメディアとして機能していた歌舞伎サイドは、虚構の中に当時のニュースをぶち込むという手法を取ることになる。忠臣蔵だと、設定をもっと昔ののお家騒動(室町時代以前なら、歴史上の事件を取り上げてもよかったため)にして、その世界の中で、赤穂浪士の討ち入りの物語を作り上げていった。
これは、悪く言えば「法の目をかいくぐる」ような行為だし、良く言えば「ルールというのは、そういうもの」という認識。例えば、ネットオカマと呼ばれるネット上で男性が女性のふりをする行為がある。何だか、やたらと嫌われる存在だけれど、これも、「ネットの向こうにいる人が誰なのかは、基本的には分からない」という事実がネットの前提だという認識があれば、別に怒るような話では無いのではないだろうか。ネットでの自分は、別の仮想人格と考えている人でさえ、ネットオカマに対して怒ったりする。ネットオカマもネットオナベ(自分を守るために男性名でネット上に存在する女性)も、仮想人格であることに変わりはないのに。
あらゆることは、「その場のルール」をどう捉えるかによって、楽しみ方が大きく変わってくる。歌舞伎を、「昔の人が作った正しい時代劇」と捉えてしまうと、史実と違うと言って怒りだす人も出てくるだろうし、ネット上では「性別については嘘をついてはいけない」と考えていれば、ネットオカマに怒ってしまう。しかし、性別を偽ってはいけない、というルールなんて最初から無いのである。あるのは、「ネットの向こうは見えない」という事実だけである。そこから、色んな楽しさも生まれるし、リスクも生まれる。しかし、「それはそういうもの」として、それを前提にして考えれば、リスクも少なくなる。ネット上の情報なんて話半分、というのが正しい姿勢かもしれないのだ。
綾辻行人の「どんどん橋、落ちた」は、そうしたルールの捉え方と、虚構内の論理とはどういうものなのか、ということについて徹底的に考えて書かれた短編集だ。ここに収録されている、いくつもの「犯人は誰だ」物語について、全ての犯人を当てることは、ほとんど無理だろう。上手く騙されて「インチキだ!」と思う人もいるだろう。でも、それは単に自分の中に勝手にルールを作り上げているからに過ぎない。
(文:納富廉邦)
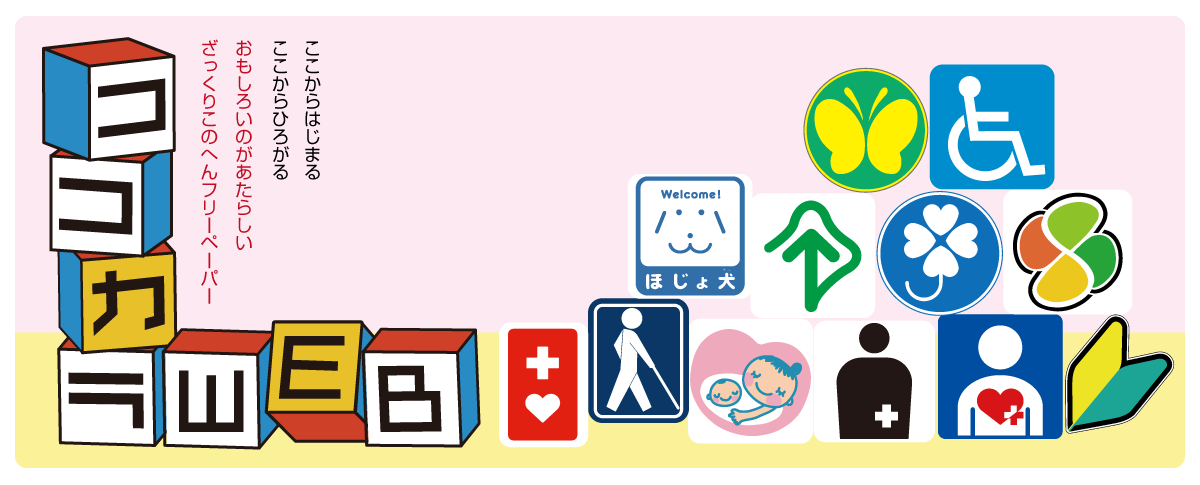

 Follow
Follow